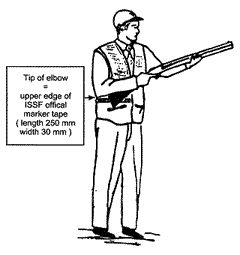魂の叫び~スキート射撃論~
スキート射撃の姿勢⑥
射撃におけるアドレスとは、射台で射手がスタンスを取り、銃床をガンポジションに付け、銃口を放出口とセンターポールとの中間点方向に向け、クレーの飛行線の高さに照星を向けた姿をとることを言います。
適切な拳銃動作に続いて、正しいスイングをして、クレーを狙わなければ命中させることはできません。
通常、射手にはアドレスを完成させるまでに、決まったルーティンがあって、毎回それを繰り返すようにしていますが、あまり射撃をしない方は、漠然と射台に入り、漫然とコールしてしまいます。
スタンスのところで強調しましたが、0の位置を定めるということは重要です。
射台にどの方向から入るかは、ゴルフのアドレスを取るときと同じく目標を見ながら入ることが大事です。
スキート射撃の場合には、どこを見て入る方向を決めたら良いでしょうか。
スキート射撃で狙うのは、当然ながらクレーです。ならばやはり放出口でしょうか。
それとも撃破予想点、それとも放出口とセンターポールとの中間点でしょうか。
ここには、まだ答えが出せていませんが、放出口とセンターポールとの中間点を正面に見るような方向から射台に入ることを心掛けています。
次に、射台のどこに立てば良いかも意味があります。
下図は、右射手の2番射台における立ち位置を示しています。
射撃論では、基本を②としていますが、私は③の位置に立っています。
①は、放出口に近づくことになりますので、見越しの距離は短くなることから有利な立ち位置と言えます。
このように立つ射手が多いことからも、合理性の高いものと考えられます。
一方、放出口を見るためには顔を左に向けなければなりません。
このため、右目がリブから離れる、顔を動かした際に、銃も動いてしまうなどの問題も発生します。
③は、放出口から遠くなりますので、見越しの距離は長くなります。
一方、放出口は顔を左に向けなくても、視野の端に放出口が見えるようになります。
さらに、撃破点までの距離が遠くなりますので、パターンが広がります。
⑤の左後側に立つことは、見越しの距離、放出口の見やすさ、パターンなどから考えても合理的とは考えにくい立ち位置となります。
6番射台では、これとは逆に右上の立ち位置が見越しの距離が短くなるので、有利になります。
私は、2番と同じ理由で⑤左後側の立ち位置をとっています。
もう一つ、射台後方の位置を使う理由は、雨天時に、先台を持つ左手が濡れないで済むという、おまけのような理由もあります。
また足の置き方は、左右対称とするのか、左脚が前、右脚が後とするのかというところも重要で、スイングや射撃時の反動などに影響します。
スイングを考えた場合には、左右のスイング幅が変化します。
極端に、脚を前後に配置したスタンスは好ましいとは思えません。
しかしながら、ここで考えたいのは、どちらの脚を基準にしてスタンスを決めるかということです。
Aタイプは前脚側に軸を作ると身体は動きやすくなり、Bタイプは後脚側に軸を作ると動きやすくなります。
私は、A1タイプなので、左脚の位置を決めた後、そこへ右脚を揃えるようにスタンスを作ります。
拳銃動作時に銃口が、撃破予想点に先回りすることを「銃が飛ぶ」とか「当てに行っている」などと表現されることが起こります。
このような症状が続くようなら、銃が動きにくくするために、逆の脚から位置決めしてみることも一策となります。